■相続
2019/04/09
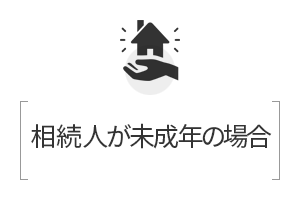
相続人が未成年者の場合の相続
相続が発生したときに、未成年の人が相続人になるケースも珍しくありません。一般的には、未成年者だけで法律行為をすることはできませんので、未成年者が相続人になった場合も特別な扱いがされることになります。
今回は、相続人の中に未成年者がいる場合の手続きや注意点についてご説明していきます。

未成年の相続人がいる場合の遺産分割協議
被相続人(亡くなった方)が亡くなると、相続人全員で「誰が、何を、どのくらい相続するか」を話し合う遺産分割協議を行います。しかし、未成年者は十分な判断能力を有していないという理由から法律上、遺産分割協議に参加することができません。
そのため、相続人の中に未成年者がいる場合は、未成年者の代わりにとなる「代理人」を立てて遺産分割協議をすることになります。
未成年者には「代理人」が必要
一般的に、相続人に未成年者がいる場合は、未成年者の親権者が代理人となります。これを「法定代理人」と言います。
しかし、未成年者の親権者も相続人である場合、親権者は法定代理人になることができません。これは、親権者が法定代理人と相続人の両方の立場を持っていると、未成年者と親権者との利益が対立してしまうからです。
例えば、未成年者の父が亡くなると、母と未成年者である子が法定相続人になります。この場合、母が子の法定代理人になると、母の相続分が増えることで子の相続分が減るという利益相反が生じてしまいます。
そこで、親権者が法定代理人になれない場合は、「特別代理人」を立てる必要があります。
特別代理人とは
特別代理人とは、未成年者の親などが家庭裁判所に申立てをして選任してもらう代理人のことです。
他の相続人との利益が対立することを防ぐため、当該相続に関係のある人(相続人など)は特別代理人になることができません。
相続人でなければ、叔父や叔母、いとこなどの親族も特別代理人になることもできますが、親族が特別代理人になると公平性を保つのが難しくなってしまいますので、専門家に依頼することをおすすめします。
なお、未成年の相続人が複数人いる場合は、その人数分だけ特別代理人を選任しなければなりません。
特別代理人を選任するには、家庭裁判所での手続きが必要です。以下では、特別代理人の選任手続きについて詳しくご説明いたします。
特別代理人の選任手続き
特別代理人の選任の申立ては、未成年者の住んでいる地域を管轄する家庭裁判所で、親権者または他の相続人が行います。
申立てに必要な書類は以下の通りです。
【申立てに必要な書類】
・特別代理人選任の申立書
・未成年者の戸籍謄本
・親権者の戸籍謄本
・特別代理人候補者の住民票または戸籍附票
・遺産分割協議書の案
この他にも、収入印紙800円分に加えて、家庭裁判所が書類送付の際に使用する郵便切手代が必要になります。必要な書類や費用は申立ての経緯や家庭裁判所によっても異なってきますので、あらかじめ申立先の家庭裁判所にお問い合わせください。
遺産分割協議書の作成方法
未成年の相続人がいる場合は、遺産分割協議書の作成方法にも違いが出てきます。
遺産分割協議がまとまると、協議の内容を遺産分割協議書に記録し、相続人全員が署名と押印をしなければなりません。しかし、未成年者は法律行為ができないため未成年者本人ではなく代理人が署名・押印を行います。
また、特別代理人選任の申立てをするときは、家庭裁判所に対して「遺産分割協議書の案」を提出します。ただし、この案が未成年者に不利な内容であった場合、特別代理人の選任が認められない可能性があります。
遺産分割の内容を考える際は、未成年者に対して最低でも法定相続分の財産を与えるようにしましょう。
未成年者が相続放棄する場合
被相続人に多額の借金がある場合や、財産があったとしても価値のない不動産だけの場合には、相続放棄をしたいと考える方が多いでしょう。
この相続放棄も法律行為ですので、未成年者が自ら行うことができません。そのため、未成年者が相続放棄を行う際は、事前に特別代理人を立てておく必要があります。
相続放棄は、相続人が相続の開始を知った日から3ヶ月以内に行わなければならないため、相続放棄を検討している場合は早めに特別代理人選任の申立てを行いましょう。
ただし、親子一緒に相続放棄をする場合は、特別代理人を選任する必要はありません。これは、親子共に相続放棄をするのであれば、親の相続人としての権利と子の代理人としての権利が対立することがなく、わざわざ特別代理人を選任する必要がないからです。
未成年者控除で相続税対策
一定以上の財産を相続する場合、相続税が課税されてしまいます。これは未成年者であっても同じです。
しかし、未成年者が相続人になっている場合に相続税が発生すると、「未成年者控除」という特別な税額控除を受けることができます。
未成年者控除を利用することができるのは、以下の条件を満たしている場合です。
【未成年者控除の利用条件】
・相続開始日に20歳未満であること
・相続または遺贈により財産を取得したこと
・法定相続人であること
・相続開始日に日本国内に住んでいること
未成年者控除の額は、「その未成年者が20歳になるまでの年数×10万円」で計算することができます。1年未満の期間は切り上げて1年として計算します。
例えば、相続開始時に14歳5ヶ月の未成年者であれば、15歳として計算されるため、5年×10万円=50万円が相続税から控除されるということです。
なお、未成年者控除額がその未成年者にかかる相続税額よりも大きい場合は、余った控除額を未成年者の扶養義務者にかかる相続税額から引くことができます。
この記事の関連記事
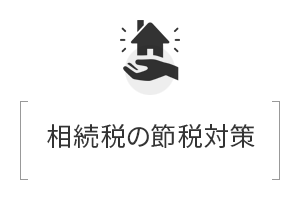
相続税の節税対策
相続税の計算を行った結果、思っていた以上に相続税がかかるケー…
相続税の計算を行った結果、思っていた以上に相続税がかかるケー…
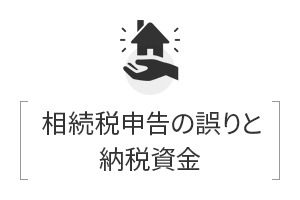
相続税申告の誤りと納税資金
相続が始まり、被相続人(亡くなった方)にある程度財産があるこ…
相続が始まり、被相続人(亡くなった方)にある程度財産があるこ…
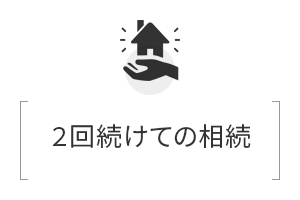
2回続けての相続
短い間に相続が2回も起こってしまう可能性があります。このよう…
短い間に相続が2回も起こってしまう可能性があります。このよう…
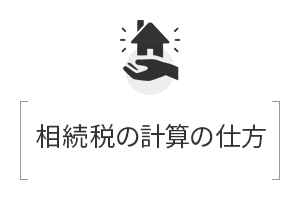
相続税の計算の仕方
相続税は、相続財産の総額から基礎控除額を差し引いた額に対して…
相続税は、相続財産の総額から基礎控除額を差し引いた額に対して…
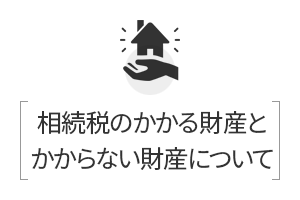
相続税のかかる財産とかからない財産
被相続人が亡くなり相続が発生すると、相続税がかかるかどうかを…
被相続人が亡くなり相続が発生すると、相続税がかかるかどうかを…
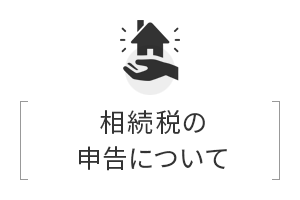
相続税の申告について
被相続人(亡くなった方)の財産を相続するとき、その財産に対し…
被相続人(亡くなった方)の財産を相続するとき、その財産に対し…

相続税について
被相続人(亡くなった方)から財産を引き継いだとき、「相続税が…
被相続人(亡くなった方)から財産を引き継いだとき、「相続税が…

贈与について
「生前贈与をすると相続税を減らすことができる」と聞いたことが…
「生前贈与をすると相続税を減らすことができる」と聞いたことが…















.jpg)

.jpg)

