■相続税
2021/04/10
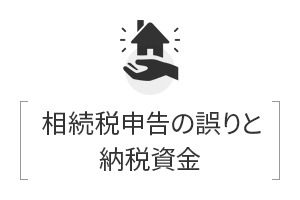
相続税申告の誤りと納税資金
相続が始まり、被相続人(亡くなった方)にある程度財産があることが分かったら、10ヶ月以内に相続税の申告・納税をしなければなりません。
もし、期限を過ぎてしまったり、申告内容にミスがあったりすると、延滞税や加算税などのペナルティが課せられる可能性があります。
しかし、相続税の申告・納税は相続人自らで税額の計算をし、申告書の作成や必要書類の収集などをしなければならないため、期限内に正確な手続きを行うのは非常に大変です。それだけではなく、期限までに納税資金を集められずに期限を過ぎてしまう可能性もあるのです。
このようなことを防ぐために、相続税申告のミスなく行うことの重要性を知り、納税資金対策についての知識を身につけておく必要があります。
今回は、相続税申告でミスをした場合のペナルティと納税資金の確保について詳しくご説明していきます。
相続税申告で誤りが起こる割合
国税庁の調査によると、2019年に亡くなった人の数は約138万人で、そのうち相続税申告書の提出にかかる人は11万5千人程でした。つまり、亡くなった人の中で相続税の申告が必要だったのは、約8%ということになります。
相続税の申告が必要な人は意外と少ないと思われがちですが、問題はここからです。
相続税の申告が必要な8%の中で、正確に申告ができている割合を調査したところ、実地調査をした12,463件のうち10,684件で相続税の申告漏れ等の違法行為にあたる非違があったことがわかりました。これは、相続税申告をしたケースの85.7%で申告ミスがあったということになります。
このように、相続税申告でミスの起こる割合は非常に高く、いかに正確な申告が難しいかがよくわかります。
では、相続税の申告ミスはどのような場合に起こりやすいのでしょうか?
相続税申告で誤りやすい財産
相続税の申告書を作成する際、特に注意したいのが「相続財産の申告漏れ」です。
申告漏れは、相続税の2割加算を考慮していなかったり、相続税がかかる財産の範囲を間違って把握していたりすることで起こります。
国税庁の調査によると、申告漏れ相続財産の総額3,474億円のうち、最も金額の多い財産が「現金・預貯金」の1,268億円、次に多いのは「土地」で422億円、「有価証券」が388億円となっており、圧倒的に現金・預貯金の申告漏れが多いことがわかりました。
現金・預貯金の申告漏れを防ぐためには、被相続人の通帳やキャッシュカードを手がかりに利用していた預金口座を残さず把握し、口座の明細からお金の流れを調査することも大切です。
また、相続税の対象となるのは被相続人名義の口座だけではありません。
例えば、名義は妻や孫になっているが通帳の管理などは被相続人が行っていた場合は、実質的な持ち主は被相続人であるとみなされ、相続税の課税対象となってしまうのです。
相続税の申告漏れのないよう、相続税の対象となる財産をしっかり把握し、隅々まで調査を行いましょう。
相続税申告の誤りによるペナルティ
相続税の申告をした後に、国税局や税務署の実地調査で申告漏れが見つかった場合、申告の修正が求められます。
このときに課せられるペナルティが「過少申告加算税」です。
過少申告加算税とは、本来納めなければならない税額よりも少ない額を申告した場合に、その差額に対して課税される税金です。
過少申告税にかかる税率は修正申告の時期によって異なり、調査通知後で税務署からの指摘がある前に自主的に申告した場合は5%(50万円を超える部分については10%)、税務署からの指摘があった後に申告した場合は10%(50万円を超える部分については15%)となっています。
この他にも、相続財産を隠して偽った申告を行ったり、意図的に申告を行わなかったりした場合は「重加算税」という重いペナルティが課せられます。
重加算税にかかる税率は、申告書の内容に隠蔽や偽装がある場合は追加納付した税額の35%、意図的に申告を行わなかった場合は追加納付した税額の40%です。
相続税の申告に誤りがあると、本来払わなくてもよい税金がかかってしまいます。無駄な税金を払わなくて済むように、財産の調査と相続税の計算は慎重に行いましょう。
納税をしないことによるペナルティ
相続税申告の誤りだけでなく、納税をしないことによるペナルティも存在します。相続税の納税は申告と同様、「相続開始から10ヶ月以内」に行わなければなりません。しかし、思った以上に相続税がかかる場合や、遺産分割に時間がかかり納税期限間近になってしまった場合など、期限までに納税資金が集められない可能性は身近に存在します。
このように、期限内に支払うべき税金を納めることができない場合は「延滞税」というペナルティが課せられます。延滞税は、納税期限の翌日から税金が完納されるまでの日数に応じて課税されますが、本税が1万円未満である場合は延滞税は発生しません。
納税資金対策の方法
先ほどご説明した通り、期限までに納税資金が集められず延滞税が課税されてしまうケースは、意外と身近に存在します。
いざ納税するときに、納税資金が足りないという事態に陥らないためには、事前に納税資金を準備しておく必要があります。
ここでは、相続が発生する前にできる納税資金対策と、相続が発生した後にできる納税資金対策をご紹介します。
【相続が発生する前にできる納税資金対策】
相続が発生してから慌てて納税資金を準備することがないように、生前のうちから対策を取っておくことが大事です。
① 財産の組み換え
納税資金の不足が予想される場合は、換金しにくい財産を生前に換金しておく方法があります。
例えば、不動産が主な財産で、ほとんど現金がない場合などがこれにあたります。不動産を多く所有していると、現金はないが多額の相続税額が必要になる可能性があるのです。
このような場合は、生前に不動産を売却し、換金しやすい金融資金等に組み換えておく方法をご検討ください。
② 生命保険に加入する
相続が発生すると被相続人の口座は凍結してしまうため、遺産分割が決まるまでは被相続人の口座からお金を下ろすことができなくなります。
しかし、被相続人が生命保険に加入しておくと、相続が発生してからすぐに成目保険金を受け取ることができ、受け取った保険金を納税資金として利用することができるのです。
③ 生前贈与を活用する
生前贈与とは、生きているうちに自分の財産を他人に贈与し、相続財産を少しでも減らしておく方法です。
「暦年課税贈与」を活用すると毎年110万円までの贈与を非課税で行うことができるため、相続税の節税になるとともに、贈与された財産を納税資金として利用することも可能になります。
【相続が発生した後にできる納税資金対策】
相続はいつ発生するかわかりません、そのため、生前のうちに十分な納税資金対策を取れない可能性も考えられます。
このように、相続が発生した後にできる対策をいくつかご紹介します。
① 金融機関からの借り入れ
金融機関から納税資金を借り入れる方法です。ただし、金融機関は審査が厳しく、担保設定費用が発生する可能性がありますので、慎重にご検討ください。
② 相続財産を売却する
不動産などの売却が可能な財産があれば、売却して納税資金を確保する方法があります。しかし、不動産の売却には時間がかかる可能性があるため注意が必要です。納税期限までに売却ができず、資金を確保できない可能性も考えられます。
③ 延納・物納
一定の要件を満たす場合は、「延納」や「物納」という方法が認められます。
延納とは現金一括での納付ができない場合に複数年で分割して支払う方法で、物納とは相続税を金銭以外のもので納める方法です。
いずれも全員に認められる方法ではありませんので、延納や物納を活用することは考えずに納税資金を確保しておきましょう。
まとめ
今回は、相続税申告の誤りによるペナルティと納税をしないことによるペナルティ、納税資金の準備方法についてご説明しました。
相続税の申告・納税は相続の開始から10ヶ月以内に行わなければならず、申告においては毎年たくさんの申告ミスが発覚しています。
期限間近になってから焦って準備をすると、申告ミスや納税資金の不足が起こってしまいますので、余裕を持った準備を心がけましょう。
この記事の関連記事
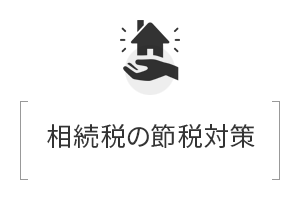
相続税の節税対策
相続税の計算を行った結果、思っていた以上に相続税がかかるケー…
相続税の計算を行った結果、思っていた以上に相続税がかかるケー…
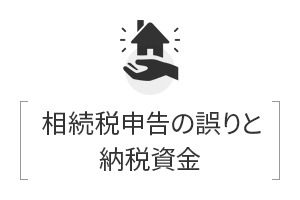
相続税申告の誤りと納税資金
相続が始まり、被相続人(亡くなった方)にある程度財産があるこ…
相続が始まり、被相続人(亡くなった方)にある程度財産があるこ…
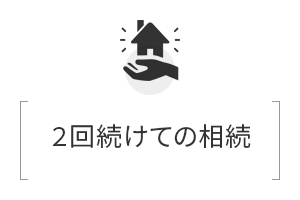
2回続けての相続
短い間に相続が2回も起こってしまう可能性があります。このよう…
短い間に相続が2回も起こってしまう可能性があります。このよう…
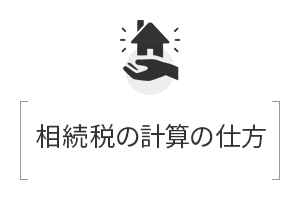
相続税の計算の仕方
相続税は、相続財産の総額から基礎控除額を差し引いた額に対して…
相続税は、相続財産の総額から基礎控除額を差し引いた額に対して…
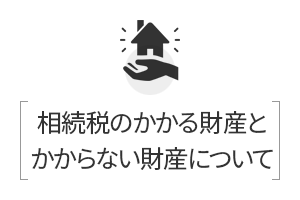
相続税のかかる財産とかからない財産
被相続人が亡くなり相続が発生すると、相続税がかかるかどうかを…
被相続人が亡くなり相続が発生すると、相続税がかかるかどうかを…
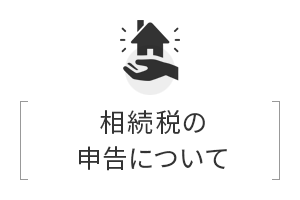
相続税の申告について
被相続人(亡くなった方)の財産を相続するとき、その財産に対し…
被相続人(亡くなった方)の財産を相続するとき、その財産に対し…

相続税について
被相続人(亡くなった方)から財産を引き継いだとき、「相続税が…
被相続人(亡くなった方)から財産を引き継いだとき、「相続税が…














.jpg)

.jpg)

.jpg)

