■相続税
2021/04/10
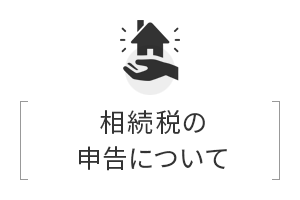
相続税の申告について
被相続人(亡くなった方)の財産を相続するとき、その財産に対して相続税がかかる場合があります。相続税がかかる場合、相続人は税務署に対して「相続税の申告」をしなければなりません。
申告には期限があり、この期限に遅れるとペナルティが課されてしまいますので、事前に申告の手順を確認しておきましょう。
今回は、相続税申告の方法や期限について詳しくご説明していきます。

相続税とは
相続税とは、相続や遺贈によって被相続人の財産を受け継いだときに、その財産に対して課される税金のことです。
しかし、財産を受け継いだからといって、全員に相続税がかかるわけではありません。平成30年の調査では、1年間に発生した5万件の相続のうち、相続税の申告が必要なのは約3千件と非常に少なく、全体のわずか6.7%しか相続税の申告を行う必要がないということがわかりました。
では、どのような人に相続税の申告が必要なのでしょうか?次項では、相続税の申告が必要なケースについてご説明します。
相続税の申告が必要なケース
相続では、相続財産の総額が一定の金額を超えるまでは相続税がかからない「相続税の基礎控除」と言う制度があります。
相続税の基礎控除は3000万円+(600万円×法定相続人の数)で計算され、相続財産の総額が基礎控除額を超える場合にのみ相続税がかかる仕組みです。したがって、相続税の申告が必要なのは「相続財産の総額が基礎控除額よりも大きい」ケースです。
なお、配偶者の税額軽減などの特例を使ったことにより相続税額が0円になった場合は、申告が必要ですのでご注意ください。
相続税申告の期限
相続税の申告が必要だとわかったら、申告の期限を確認しましょう。相続税申告の期限は「相続があったことを知った日の翌日から10ヶ月以内」です。
例えば、被相続人が2月1日に亡くなったとしたら、その年の12月1日が相続税の申告期限日となります。ただし、遠方に住んでいる人や疎遠になっている人は、被相続人が亡くなった事実を知るまでに期間が空いてしまうかもしれません。そのような場合は、葬式の通知や亡くなった旨の通知を受けた日の翌日から10ヶ月を数えます。
なお、期限日が土日・祝日の場合は、次にくる平日が期限日となります。
相続税の申告の流れ
相続が発生してから相続税の申告をするまでの流れは、以下の通りです。
流れ① 相続財産の調査
まずは、被相続人がどのような財産をどのくらい持っているかを調査する必要があります。大きくてわかりやすい不動産や預貯金だけでなく、時計や美術品、日常的に使っていたペンなども相続財産に含まれますので、隅々まで調査しましょう。また、借金などのマイナスの財産も相続財産に該当します。特に、マイナスの財産は家族から見つからないように隠している可能性も考えられるため、調査漏れがないかしっかりと確認しましょう。
流れ② 遺産分割協議をする
相続財産が明らかになったら、相続人全員で「遺産分割協議」を行います。遺産分割協議とは、被相続人の財産について「誰が、何を、どのくらい相続するか」を話し合いで決めることです。
遺産分割が決まらなければ相続税額を計算することができませんので、なるべく早めに協議を成立させましょう。
流れ③ 相続税の計算をし、申告書を作成
遺産分割協議が成立したら、その内容に基づいて誰がどのくらいの相続税を負担するのかを計算します。それぞれが納めるべき相続税を算出した後に「相続税の申告書」を作成し、相続人・受遺者全員が署名捺印をします。
なお、配偶者の税額軽減を適用する場合は、申告書の第5表「配偶者の税額軽減額の計算書」に必要事項を記入してください。
流れ④ 相続税の申告
相続税の申告書を作成したら、いよいよ相続税の申告をします。申告は被相続人の住所地を管轄する税務署に対して、相続人が共同して申告書を提出して行います。無事に申告が完了したら、お近くの金融機関または管轄の税務署で納税の手続きをしましょう。
相続税申告に必要な書類
相続税申告に必要な書類は以下の通りです。
相続関係を明らかにする書類
・被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
・被相続人の住民票の除票
・被相続人の死亡診断書のコピー
・相続人全員の戸籍謄本
・相続人全員の住民票
・相続人全員の印鑑証明書
・遺言書または遺産分割協議書
・相続人および受遺者のマイナンバー確認ができる書類
・相続人および受遺者の本人確認書類
相続手続きでは「被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本」を揃える必要があります。戸籍謄本とは、同じ籍に在籍している人の結婚や離婚、転籍などについて記録されている公文書のことです。戸籍謄本は本籍地の役所で取得することができますので、被相続人の死亡時の本籍地の役所で最終の戸籍謄本を取得し、その内容をチェックして転籍があれば転籍前の役所で戸籍謄本を取得します。これを繰り返し、出生までのすべての戸籍謄本を収集しなければなりません。
財産内容を明らかにする書類
相続関係を明らかにする書類の他に、相続財産の内容を明らかにする書類も提出しなければなりません。被相続人の持っていた財産ごとに、以下の書類が必要となります。
【土地や建物などの不動産】
登記簿謄本、固定資産評価証明書、実測図、地積測量図または公図の写し、賃貸の場合は賃貸借契約書
【現金や預貯金】
預金残高証明書、既経過利息計算書、通帳の写しまたは出入金明細書
【有価証券等】
残高証明書、株券の写し、配当金通知書など
【生命保険金や死亡退職金】
生命保険金の場合は、保険金支払通知書、保険証書の写し、解約返戻金相当額証明書
死亡退職金の場合は、退職金支払通知書の写しなど
【借金などの債務】
被相続人に借入金がある場合は金銭消費貸借契約書の写し、尺集残高証明書
未払金がある場合はその請求書、未納の税金がある場合は課税通知書・納付書
相続税申告をしなかったら
相続税の申告が必要であるにもかかわらず、期限内に申告をしなかった場合はペナルティが課されてしまいます。災害や交通の途絶、その他やむを得ない理由があり期限に間に合わなかった場合以外は正当な理由なく申告をしていないことになり、ペナルティの対象です。
例えば、相続人同士の仲が悪く遺産分割協議がなかなか決まらないまま10ヶ月の期限が過ぎてしまった場合は、正当な理由とはなりません。
このように、10ヶ月を過ぎても相続税の申告をしなかった場合は「無申告加算税」が課されてしまいます。国税庁によると、無申告加算税は納税すべき税額の50万円までの部分には最大15%、50万円を超える部分には最大20%の加算税がかかることになっています。
財産を隠して意図的に相続税の申告をしなかった場合など、特に悪質な場合は「重加算税」というさらに重いペナルティが課されます。
無駄な税金までを支払わなくて済むように、スムーズで正確な相続税申告を実現しましょう。
まとめ
今回は相続税申告の流れや期限についてご説明しました。
相続税がかかる場合は税務署に対して申告が必要ですが、申告をするまでに相続財産の調査をしたり遺産分割協議をしたりと、やるべきことが多くあります。
申告の期限を過ぎてしまうと重いペナルティが課されてしまいますので、相続が発生したらできるだけ早めに手続きを進め、余裕を持って申告をしましょう。
この記事の関連記事
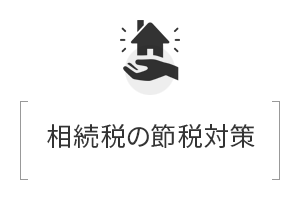
相続税の節税対策
相続税の計算を行った結果、思っていた以上に相続税がかかるケー…
相続税の計算を行った結果、思っていた以上に相続税がかかるケー…
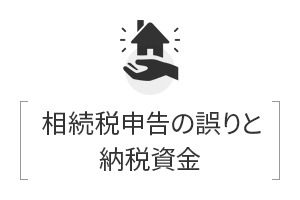
相続税申告の誤りと納税資金
相続が始まり、被相続人(亡くなった方)にある程度財産があるこ…
相続が始まり、被相続人(亡くなった方)にある程度財産があるこ…
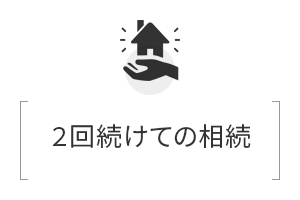
2回続けての相続
短い間に相続が2回も起こってしまう可能性があります。このよう…
短い間に相続が2回も起こってしまう可能性があります。このよう…
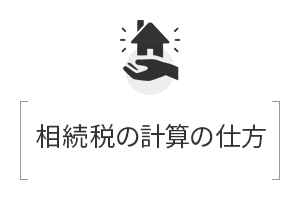
相続税の計算の仕方
相続税は、相続財産の総額から基礎控除額を差し引いた額に対して…
相続税は、相続財産の総額から基礎控除額を差し引いた額に対して…
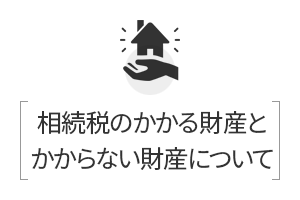
相続税のかかる財産とかからない財産
被相続人が亡くなり相続が発生すると、相続税がかかるかどうかを…
被相続人が亡くなり相続が発生すると、相続税がかかるかどうかを…
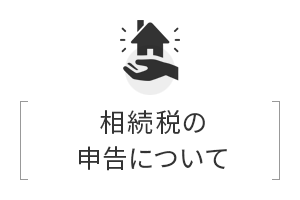
相続税の申告について
被相続人(亡くなった方)の財産を相続するとき、その財産に対し…
被相続人(亡くなった方)の財産を相続するとき、その財産に対し…

相続税について
被相続人(亡くなった方)から財産を引き継いだとき、「相続税が…
被相続人(亡くなった方)から財産を引き継いだとき、「相続税が…















.jpg)

.jpg)

