■相続税
2021/04/10

相続税について
被相続人(亡くなった方)から財産を引き継いだとき、「相続税がかかるかどうか」「いくらかかるのか」に関心が集まります。
実は、年間5万件近くの相続が発生している中で、相続税のかかる相続は全体の6.7%ほど(平成30年時点)と、非常に少ないのが現状です。しかし、相続税の知識がないままでは、相続税がかかることが分かってから慌てて納税資金を集めることになるかもしれません。
相続税についての知識を持っておくことは、円滑な相続手続きが実現できるだけでなく、早い段階での節税対策につながる可能性があります。
今回は、相続税の仕組みについて説明していきます。

相続税とは
相続税とは、簡単に言うと被相続人から引き継いだ財産に対してかかる税金のことです。
例えば、1億円の財産を持っているAさんが亡くなったとしましょう。Aさんが持っていた財産は、亡くなった時点でAさんの身内に引き継がれることになります。
これを相続といい、受け継がれる財産のことを相続財産といいます。
そして、この相続財産にかかる税金が「相続税」です。
被相続人から遺贈を受けた場合も同様です。
遺贈とは遺言によって相続人以外の人に財産を贈ることで、被相続人から財産を引き継いでいることになるため、相続税の課税対象となります。例えば、被相続人の残した遺言に「友人の〇〇に甲不動産を贈与する」と書かれていた場合、甲不動産は友人に遺贈されたことになり、その財産には相続税がかかります。
相続税のしくみ
相続税とは、相続や遺贈によって財産を引き継いだときに、その財産に対してかかる税金です。しかし、財産を引き継いだからといって全員に対して相続税が課されるわけではありません。相続税は、相続財産の総額が一定の額を超えた場合にのみ相続税が課される仕組みになっています。
この額を「相続税の基礎控除」といい、全ての相続に対して適用されます。
そのため、相続財産が基礎控除額を超えない範囲であれば、相続税を納める必要がないのです。
相続税の基礎控除とは 相続税の基礎控除とは、相続税の計算をする上で相続財産の総額から差し引くことができる額のことです。基礎控除額は「3000万円+(600万円×法定相続人の数)」で計算され、相続財産の総額が基礎控除額を超えた範囲にのみ相続税が課されます。 例えば、被相続人に1億円の財産があり、法定相続人は妻と長男、次男のみのケースを考えてみましょう。 法定相続人は合計3人ですので、基礎控除額は3000万円+(600万円×3人)=4800万円となります。したがって、財産1億円から控除額4800万円を差し引いた5200万円に対して相続税がかかることになります。
基礎控除の計算式を見てみると、法定相続人の数が多ければ多いほど、控除額が大きくなることが分かります。では、どのような人が「法定相続人」に該当するのでしょうか?
法定相続人とは
法定相続人とは、被相続人の財産を引き継ぐことが民法によって認められている人のことです。法定相続人になれるのは、被相続人の配偶者と血族に限られ、配偶者は常に法定相続人になることができます。しかし、血族の場合は優先順位が定められており、順位の高い人から相続人になることができます。血族の優先順位は次の通りです。
第1順位:子や孫などの直系卑属
被相続人に子がいる場合は、子が法定相続人になります。
なお、子が被相続人よりも前に亡くなっている場合は、亡くなった子の子(被相続人からみた孫)が代わりに相続人となります。これを「代襲相続」といいます。
第2順位:父母や祖父母などの直系尊属
被相続人に子や孫がいなければ、父母や祖父母などの直系尊属が法定相続人となります。父母が被相続人よりも前に亡くなっており祖父母がご存命の場合は祖父母が法定相続人となりますが、父母と祖父母がどちらもご存命の場合は、被相続人に最も親等の近しい人(この場合は父母)が法定相続人となります。
第3順位:兄弟姉妹
被相続人に子や孫などがおらず、直系尊属もすでに亡くなっている場合は、被相続人の兄弟姉妹が法定相続人となります。
なお、兄弟姉妹が被相続人よりも前に亡くなっている場合、亡くなった兄弟姉妹の子(被相続人からみた甥・姪)が代襲相続します。
ただし、兄弟姉妹の代襲相続は甥・姪の一代に限りますので、甥・姪も亡くなっている場合の再代襲は起こりません。

相続税の計算方法
相続財産の総額が基礎控除額を超え、相続税がかかることが明らかになった場合は相続税額を計算します。
相続税の計算方法は以下の通りです。具体例を交えた詳しい計算方法は別の記事で説明していますので、そちらもぜひ参考にしてください。
⑴相続税の課税対象額を法定相続分で分ける
⑵それぞれに相続税率を掛けて税額を計算する
⑶⑵で求めた税額を足して相続税の全額を求める
⑷⑶で求めた相続税の全額を実際の取得割合に応じて分ける
⑸配偶者の税額軽減など各種税額控除を差し引いて、実際に負担する税額を計算する
相続税率の速算表
(表が入ります)
配偶者の税額軽減とは
配偶者の税額軽減とは、配偶者が相続や遺贈により引き継いだ財産額が1億6000万円、もしくは配偶者の法定相続分相当額のどちらか多い方の金額までは配偶者に相続税がかからない制度のことです。
配偶者の税額軽減を適用するためには、被相続人の戸籍上の配偶者であれば婚姻期間の長さは問われません。しかし、内縁の妻・夫の場合は適用することができませんのでご注意ください。
配偶者の税額軽減を適用した結果、配偶者の相続税額が0円になったとしても、相続税の申告は行う必要があります。したがって、相続税の申告までに必要書類の準備を済ませておきましょう。
相続税の申告と納税について
相続税額が分かったら、税務署に対して相続税の申告・納税をします。申告・納税の期限は「相続の開始があったことを知った時から10ヶ月以内」と定められており、この期限を過ぎると延滞税や加算税などのペナルティが課されてしまいます。
また、相続税の納税方法は現金一括払いです。被相続人に現金や預貯金などの財産が少なく、不動産などの換金が必要な財産が多い場合は、相続税額が高い割に納税資金に使えるお金がないケースもありますので、なるべく早い段階で相続税の計算と納税資金の確保をしておきましょう。
なお、そもそも相続税がかからない場合は相続税の申告をする必要はありません。
まとめ
今回は相続税について、基礎控除や計算方法などを簡単にご説明しました。相続税に関する知識は、ある程度財産を持っている家庭にしか関係ないと思われがちですが、知識があることでトラブルの防止や節税対策につながる可能性もあります。
相続の対策に早過ぎることはありません。今のうちに知識を身につけて円満な相続を実現しましょう。
この記事の関連記事
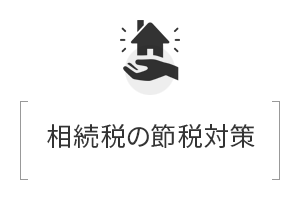
相続税の節税対策
相続税の計算を行った結果、思っていた以上に相続税がかかるケー…
相続税の計算を行った結果、思っていた以上に相続税がかかるケー…
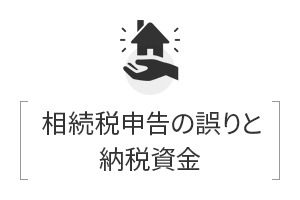
相続税申告の誤りと納税資金
相続が始まり、被相続人(亡くなった方)にある程度財産があるこ…
相続が始まり、被相続人(亡くなった方)にある程度財産があるこ…
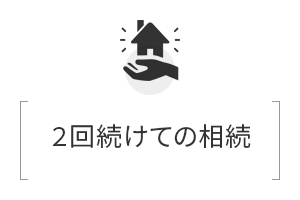
2回続けての相続
短い間に相続が2回も起こってしまう可能性があります。このよう…
短い間に相続が2回も起こってしまう可能性があります。このよう…
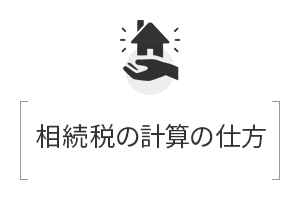
相続税の計算の仕方
相続税は、相続財産の総額から基礎控除額を差し引いた額に対して…
相続税は、相続財産の総額から基礎控除額を差し引いた額に対して…
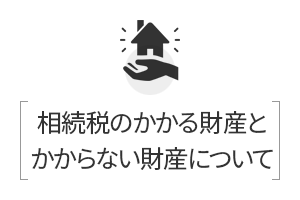
相続税のかかる財産とかからない財産
被相続人が亡くなり相続が発生すると、相続税がかかるかどうかを…
被相続人が亡くなり相続が発生すると、相続税がかかるかどうかを…
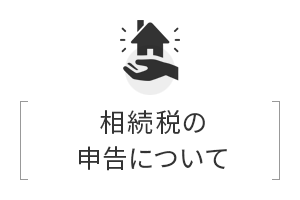
相続税の申告について
被相続人(亡くなった方)の財産を相続するとき、その財産に対し…
被相続人(亡くなった方)の財産を相続するとき、その財産に対し…

相続税について
被相続人(亡くなった方)から財産を引き継いだとき、「相続税が…
被相続人(亡くなった方)から財産を引き継いだとき、「相続税が…















.jpg)

.jpg)

