■相続税
2021/04/10
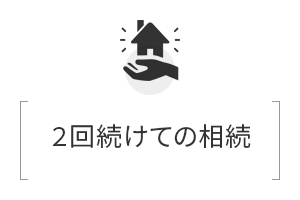
2回続けての相続
短い間に相続が2回も起こってしまう可能性があります。このような場合、相続人は悲しみに暮れる暇もなく、2回分の相続手続きを行わなければなりません。しかし、相続人と被相続人の関係から、2回の相続でどのように財産が移っていくかわからない方も多いと思います。
例えば、祖父が亡くなった後に、祖父の財産を相続するはずだった父が亡くなってしまった場合、祖父の財産はどうなってしまうのでしょうか?また、父の分も二重に相続税を払わなければならないのでしょうか?
今回は、立て続けに相続が起こった場合の手続きや、相続税の計算について詳しく説明していきます。

数次相続とは
数次相続とは、被相続人(亡くなった方)が死亡してから、遺産分割協議や財産の名義変更などが終わらないうちに、相続人が死亡するケースのことをいいます。
例えば、被相続人が亡くなり、妻Aと長男Bが相続人になったケースを考えてみましょう。この相続の遺産分割協議が終わらないうちに、今度は長男Bが亡くなり、長男Bの妻Cと子Dが相続人になったとします。
この場合、初めの相続を「一次相続」、2回目の相続を「二次相続」といいます。
一次相続でBが相続するはずだった被相続人の財産は、 Bの相続人であるCとDが相続することになります。まだ一次相続の遺産分割協議を終わっていないので、A、C、Dの3人で話し合いをして被相続人の財産を分け合うことになるのです。
再転相続とは
再転相続とは、被相続人が死亡した後、相続人が被相続人の財産を相続するか(承認)、または相続しないか(放棄)を選択する前に死亡するケースのことをいいます。
相続の承認または放棄は、被相続人の死亡を知った日から3ヶ月以内に選択する必要があります。
一次相続で選択する前に死亡してしまった場合は、二次相続の相続人が一次相続の承認または放棄を選択することができます。
例えば、被相続人が亡くなり、妻Aと長男Bが相続人になったケースを考えてみましょう。長男Bが被相続人の財産を相続するか放棄するか選択する前に亡くなり、長男Bの妻Cと子Dが相続人になったとします。
この場合、Bが選択するはずであった承認または放棄を、Bの相続人C、Dが選択することができるのです。
したがって、CとDは一次相続と二次相続両方の承認・放棄を選択することができます。
しかし、注意してほしいのが「二次相続を放棄してしまったら一次相続の承認ができない」ということです。これは、一次相続の承認・放棄を選択する権利を長男Bから相続することになるため、Bの相続を放棄する選択をした時点で、被相続人の相続をする権利がなくなってしまうからです。
相次相続とは
相次相続とは、一次相続から10年以内に相続人が亡くなり、新たな相続が発生するケースです。
数次相続とは異なり、遺産分割協議や名義変更などの手続きが終わっているかどうかは問題ではなく、このケースでは主に相続税法上の観点から問題が発生します。
例えば、一次相続で父が亡くなり、それから10年も経たずに母が亡くなった場合を考えてみます。この場合、母は父の相続人となるため、一次相続で父の財産を相続しています。その後、10年以内に母も亡くなったとなると、母が相続した父の財産には、短い間に相続税が2回も課税されることになるのです。
このようなケースで、相続人が支払う相続税の負担を軽減するために、「相次相続控除」という制度があります。
相次相続控除の適用
相次相続控除とは、一次相続から10年以内に二次相続が発生した場合に、相続税の負担が過重になるのを軽減する制度です。
相次相続控除を適用すると、例えば、父から財産を相続した母が父の死後10年以内に死亡してしまった場合、母が父の相続で支払った相続税額の一部が、子が母の相続で支払うべき相続税から控除されます。
一次相続から二次相続までの期間が短ければ短いほど、控除される額は大きくなっていく仕組みです。しかし、控除はある一定の要件を満たしている人でなければ受けることができません。控除が受けられる人の要件は次の通りです。
相次相続控除が受けられる人
相次相続控除が受けられるのは、次の全ての要件に当てはまる人です。
・被相続人の相続人であること
・二次相続の開始前10年以内に開始した一次相続により被相続人が財産を取得していること
・二次相続の開始前10年以内に開始された一次相続により取得した財産について、被相続人に対して相続税が課税されたこと
この控除が受けるためには、亡くなった方の相続人であることが要件です。仮に、遺言により財産を受け取っていたとしても、相続人でなければこの控除は受けられませんので、ご注意ください。
相次相続控除額の計算方法
相次相続控除の金額は以下の計算式によって求められます。
A×C/(B−A)×D/C×(10−E)/10=各相続人の相次相続控除額
※A×C/(B−A)が100/100を超える場合は100/100とする。
上の式のA〜Eは以下の数字を当てはめて計算します。
A:二次相続の被相続人が一次相続の際に課せられた相続税額
この相続税額は、相続時精算課税を利用した際に納付した贈与税を控除した後の金額であって、納税の猶予で免除された相続税額は含まれないのでご注意ください。
B:二次相続の被相続人が一次相続の際に取得した純資産価額
※ 純資産価額とは、取得した相続財産と相続時精算課税を適用した財産の価額を足し合わせた金額から、借金などの債務や葬式費用を差し引いた金額のことです。
C:二次相続での相続や遺贈、相続時精算課税にかかる贈与によって財産を取得した全ての人の純資産価額の合計額
D:相次相続控除の適用を受ける相続人が取得した財産の価額
E:一次相続から二次相続までの期間(1年未満の期間は切り捨て)
二次相続を見据えた対策
相次相続控除があるとはいっても、相続税が多く課されてしまうことには変わりありません。相続税を少しでも抑えるためには、二次相続を見据えた生前対策を取っておく必要があるのです。
対策① 生前贈与の活用
生前贈与とは、生前のうちに自分の財産を他人に贈与し、相続税の課税対象となる財産を減らしておくことをいいます。
最も節税効果が高いのが、年間110万円までの贈与が非課税となる「暦年課税」です。
例えば、4人の子に毎年100万円の贈与を行うとしたら、1年間で400万円、10年間で4,000万円もの財産を贈与することができます。暦年課税は毎年コツコツと贈与を行うことで、大きな節税効果が期待できる方法ですので、早いうちに始めておきましょう。
対策② 配偶者の相続分を少なくする
配偶者には相続税の税額軽減制度があるため、一次相続では配偶者に多く財産を相続させれば、相続税が抑えられると思われがちです。
しかし、配偶者の資産が増えると、今度は二次相続で相続の対象となる財産が増えることになります。そのため、総合的には、一次相続で配偶者の資産をなるべく増やさないようにすることで節税につながるのです。
子や孫に多く相続させるなど、二次相続を見据えた工夫が必要になります。
まとめ
今回は、2回続けて相続が起きた場合の財産の流れや、相続税の計算についてご説明しました。
2回続けての相続には「数次相続」、「再転相続」、「相次相続」があり、それぞれ相続が発生した時期や状況によって分類が異なります。立て続けに相続が起こった場合でも、慌てずに的確な対応を取れるように、二次相続を見据えた対策を取っておくことをおすすめします。
この記事の関連記事
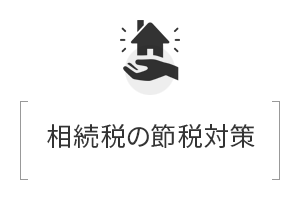
相続税の節税対策
相続税の計算を行った結果、思っていた以上に相続税がかかるケー…
相続税の計算を行った結果、思っていた以上に相続税がかかるケー…
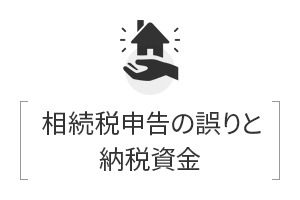
相続税申告の誤りと納税資金
相続が始まり、被相続人(亡くなった方)にある程度財産があるこ…
相続が始まり、被相続人(亡くなった方)にある程度財産があるこ…
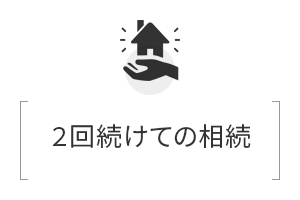
2回続けての相続
短い間に相続が2回も起こってしまう可能性があります。このよう…
短い間に相続が2回も起こってしまう可能性があります。このよう…
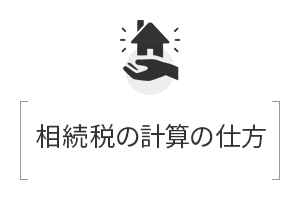
相続税の計算の仕方
相続税は、相続財産の総額から基礎控除額を差し引いた額に対して…
相続税は、相続財産の総額から基礎控除額を差し引いた額に対して…
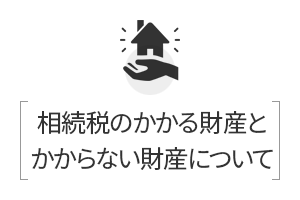
相続税のかかる財産とかからない財産
被相続人が亡くなり相続が発生すると、相続税がかかるかどうかを…
被相続人が亡くなり相続が発生すると、相続税がかかるかどうかを…
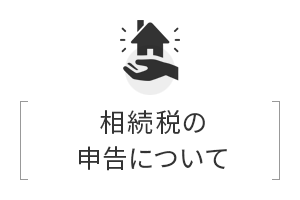
相続税の申告について
被相続人(亡くなった方)の財産を相続するとき、その財産に対し…
被相続人(亡くなった方)の財産を相続するとき、その財産に対し…

相続税について
被相続人(亡くなった方)から財産を引き継いだとき、「相続税が…
被相続人(亡くなった方)から財産を引き継いだとき、「相続税が…















.jpg)

.jpg)

