■相続税
2021/04/10
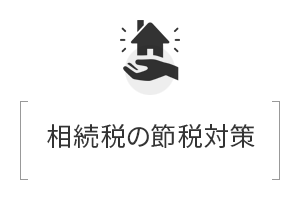
相続税の節税対策
相続税の計算を行った結果、思っていた以上に相続税がかかるケースは珍しくありません。しかし、相続税は生前の準備次第では大幅な減額が期待できる税金です。「まだ元気なのに死後のことを考えるなんて」と思う方も多いと思いますが、実際に相続税の節税は準備期間が長ければ長いだけ効果があります。残された家族に手間や負担をかけさせないためにも、相続に備えた対策を生前からとっておくことは非常に重要なのです。
今回は、生前に行う相続税の節税対策をいくつかご紹介していきます。

対策① 毎年110万円の生前贈与で相続財産を減らす
相続税は被相続人の所有している財産の総額に対して課税されるため、財産の総額が低いほど相続税額も小さくなります。生前贈与とは、被相続人が生前に自分の財産を他人に贈与しておくことで財産の総額を小さくし、相続税の節税をする方法です。
財産を効果的に贈与する方法として「暦年課税」という制度があります。暦年課税は、一人あたり年間110万円までであれば贈与税を支払わずに贈与できる制度です。
例えば、被相続人が4人の孫に毎年100万円ずつ贈与するケースを考えてみましょう。この場合、被相続人の財産は1年で400万円、10年で4000万円をも減らすことができるのです。
ただし、暦年課税を利用する際にはいくつかの注意点があります。
1つは、毎年同じ時期に同じ額を贈与していると連年贈与とみなされ、高額の贈与税が請求される可能性があることです。贈与の時期や金額を少しずつ変えるなど、連年贈与を疑われないような工夫をしましょう。
また、被相続人の死亡前3年以内に行われた贈与は相続税の課税対象となってしまう点も注意が必要です。これは、死亡する直前に駆け込みで贈与をするのを防ぐためです。
駆け込みでの贈与はなるべく避け、元気なうちから計画的に贈与をしておくことをおすすめします。
対策② 小規模宅地等の特例で評価額を80%減額
小規模宅地等の特例とは、被相続人が住んでいた土地や事業で使っていた土地、貸していた土地を一定の要件を満たす人が相続した際にその土地の評価額を下げることができる特例です。
具体的には、配偶者や同居していた人が被相続人の住んでいた土地を相続する場合、330㎡までの部分については評価額を80%減額することができます。
例えば、法定相続人が妻と長男の2人で、被相続人の財産は300㎡で5000万円の宅地のみのケースを考えてみましょう。小規模宅地の特例を適用すると、土地の評価額は5000万円×80%=1000万円になります。
相続税の基礎控除額は3000万円+(600万円×2人)=4200万円なので、相続財産の総額が基礎控除額以内となり、相続税が0円になります。
小規模宅地等の特例の適用には、限度面積や要件があります。適用できるか不安な場合は、専門家への相談をご検討ください。
対策③ 生命保険金の非課税枠を活用
生命保険金は、被相続人が亡くなったことにより保険会社から支払われるお金です。
受け取った生命保険金は相続財産に加算され、相続税の課税対象となりますが、受取人が相続人に指定されている場合は「500万円×法定相続人の数」の非課税枠を利用することができます。
例えば、法定相続人が妻と長男、次男の3人で、被相続人が保険金の受取人を長男に指定した生命保険に加入していたケースを考えてみましょう。生命保険金の金額が2000万円だとすると、生命保険金の非課税枠は500万円×3人=1500万円ですので、2000万円から非課税枠の1500万円を差し引いた500万円が相続税の課税対象となります。
対策④ 養子縁組をして法定相続人を増やす
相続税には「3000万円+(600万円×法定相続人の数)」で計算される基礎控除があり、相続税は相続財産の総額から基礎控除額を差し引いた額に対して課税される仕組みになっています。つまり、基礎控除額が増えれば増えるほど相続税額が低くなるのです。
そこで、養子縁組をして法定相続人となる子を増やし、基礎控除額を増やす節税方法があります。
養子縁組とは、血縁関係とは無関係に親子関係を生じさせることができる制度です。
たくさん養子縁組をすれば、法定相続人が増えてその分節税につながりますが、相続税法上では養子縁組の人数に制限がありますのでご注意ください。被相続人に実子がいない場合は養子2人まで、実子がいる場合は養子1人までは法定相続人の対象となります。
明らかに節税のための養子縁組であると判断されると、法定相続人として認められない可能性もあります。そのため、養子縁組を行う際は慎重になりましょう。
対策⑤ 墓地や仏具を購入しておく
墓地や墓石、仏壇・仏具などの祭祀財産には相続税がかかりません。そのため、被相続人が生前にこれらの祭祀財産を購入しておくことで、相続税のかかる現金を減らし、相続税の節税をすることができるのです。
例えば、被相続人が2000万円の現金を所有している状態で亡くなると相続財産は2000万円になりますが、生前に700万円分の祭祀財産を購入してから亡くなると、祭祀財産は相続財産に含まれないため、相続財産は現金1300万円のみとなります。
ただし、祭祀財産を生前に購入したものの代金をまだ払い終えていないという場合には、相続財産から差し引くことができません。節税対策を有効にするためには、亡くなる前にローンを払い終えるようにしましょう。
また、あまりにも高価な仏像や骨董品などは非課税財産として認められない可能性がありますのでご注意ください。
対策⑥ 更地にアパートを建てて土地の評価額を下げる
これは、被相続人が土地を所有している場合に活用できる節税対策です。では、なぜ持っている土地にアパートを建てると節税することができるのでしょうか?
アパートを建てることによる節税効果には、以下の3点があります。
1つ目は、土地の評価額が低くなることです。相続税を計算する上で、土地の大きさや形状、利用状況などの様々な事情によって評価額は下がります。土地の上にアパートが建築されると、その土地は「貸家建付地」という扱いになり、更地と比べて評価額を下げることができるのです。
2つ目は、建物の評価額も下がることです。相続税を計算する上で、建物は利用状況によって評価額が下がります。アパートは貸家ですので、建物の評価額から借家権(一律30%)を差し引いて計算することができるのです。
3つ目は、アパートを建てる際に金融機関から借り入れをすることで、借入金を相続財産から控除することができる点です。
例えば、更地に1億円のアパートを建てるために、銀行から1億円を借り入れたとします。
建物については固定資産税評価額を評価額とするため、建物価格の5〜6割程度となります。したがって、アパートの引き渡し時点では建物の評価額は約6000万円となり、相続財産を4000万円ほど減らすことができるのです。
また、土地の評価額も更地の場合より下がるので、大幅な節税が期待できます。
ただし、アパートの経営には空室リスクがあります。入居率が低いと評価額の減額幅も小さくなってしまいますので、計画的な経営を行うようにしましょう。
まとめ
今回は、相続税の節税対策の方法をいくつかご紹介しました。
節税対策は相続税を減らすことができるほか、残された家族の争いを防止することもできます。できるだけ早い段階で対策を取っておくことで、大幅な節税と円満な相続を実現しましょう。
この記事の関連記事
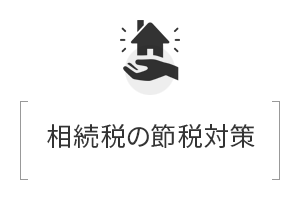
相続税の節税対策
相続税の計算を行った結果、思っていた以上に相続税がかかるケー…
相続税の計算を行った結果、思っていた以上に相続税がかかるケー…
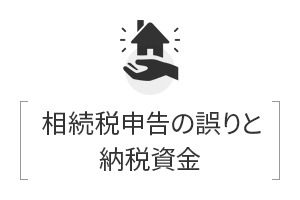
相続税申告の誤りと納税資金
相続が始まり、被相続人(亡くなった方)にある程度財産があるこ…
相続が始まり、被相続人(亡くなった方)にある程度財産があるこ…
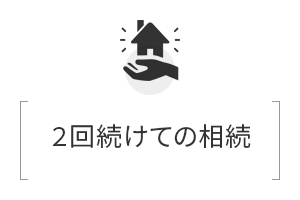
2回続けての相続
短い間に相続が2回も起こってしまう可能性があります。このよう…
短い間に相続が2回も起こってしまう可能性があります。このよう…
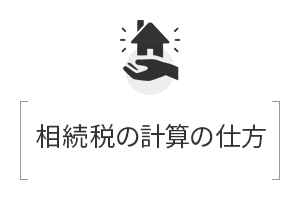
相続税の計算の仕方
相続税は、相続財産の総額から基礎控除額を差し引いた額に対して…
相続税は、相続財産の総額から基礎控除額を差し引いた額に対して…
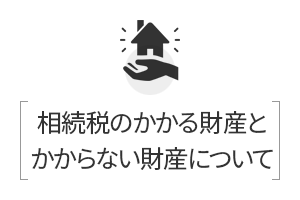
相続税のかかる財産とかからない財産
被相続人が亡くなり相続が発生すると、相続税がかかるかどうかを…
被相続人が亡くなり相続が発生すると、相続税がかかるかどうかを…
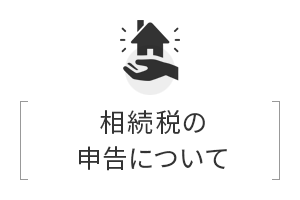
相続税の申告について
被相続人(亡くなった方)の財産を相続するとき、その財産に対し…
被相続人(亡くなった方)の財産を相続するとき、その財産に対し…

相続税について
被相続人(亡くなった方)から財産を引き継いだとき、「相続税が…
被相続人(亡くなった方)から財産を引き継いだとき、「相続税が…















.jpg)

.jpg)

